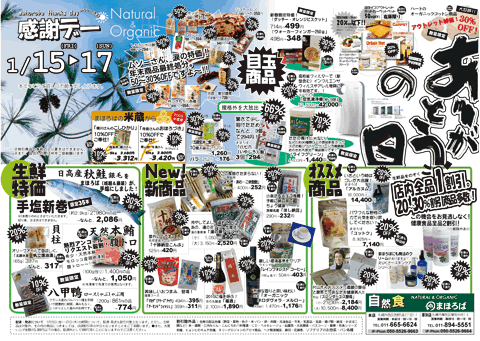ベートーベンの第九といえば、フルトベングラー指揮の名盤が思い起こされる。
戦火の元でのバイロイト祝祭管&合唱団の命がけのライブ録音。
これに勝る演奏は、遂に現われないだろうと言われている。
そのソリストの一人が不世出の名ソプラノ、若き日のエリザベート・シュヴァルツコップだった。
伝説の彼女は、技量・容貌とも女性歌手の永遠の憧れであり、目標であり続けた。

そのシュヴァルツコップが、45年ほど前、札幌市民会館で独唱会を開いたのだ。
当時高校生だった私は、楽屋に行ってサインをしてもらったそれは夢のステージだった。
ブラームスやヴォルフ、R・シュトラウスと、その歌の記憶は生涯に残る宝物だった。
鮮烈の余り、それ以来、歌曲に興味や聴く機会が失われていた。

(Elisabeth Schwarzkopf 1915年12月9日 - 2006年8月3日)
それと言うのも、日本歌曲に何故か違和感を感じていた。
オペラやリートの歌い振りでは、日本語を表現することに無理があるように思えていた。
期待してCDを聴いても、ほとんどは一回きりで、その後は聴くに耐えなかった。
あのように大声で朗々と唄う事自体、日本の詩語や情緒とはそぐわない、
やはり、地唄や座敷唄が最も相応しいと考えていた。

ところが、先日ラジオから流れて来た日本歌曲に、何とも心が惹き付けられた。
その歌手は栗本尊子さん。当年90歳の美しいおばあちゃまであった(失礼)。
カイルベルト指揮のN響で第九を伊藤京子さんと歌ったとあるから昔聴いていたのだろう。
それはクラシックの歌唱法には違いないのだけれど、何度も聴きたくなる何かが籠もっていた。
戦前生まれの方の日本語の発声の違い、音色の美しさから来るものなのかとも思った。
しかしそうではなく、やはり一語一音に特別な温かい心が溢れている、としか言いようがなかった。
そこは90年の人生の歩みの、酸いも甘いも噛み締めた滲み出る生への讃歌なのだろう。
声楽家の畑中良輔氏が「栗本尊子の声は、日本音楽界の奇蹟です」と賞賛したように、
私も、その表現力の尊さ、潔さ、美しさには、音楽の領域を越えて感動してしまった。
何度も何度も聴いても、また聴きたい衝動にかられるCDは滅多にあるものではない。
それは、まさにシュヴァルツコップを髣髴とさせる大輪の花の香と輝きだった。
3年前に出された「愛と祈り〜歌いつがれる日本のうた」に、馴染みのある
「赤とんぼ、さくらさくら、中国地方の子守唄、荒城の月、からたちの花、この道」など、
作曲家・山田耕筰氏や中田喜直さんの名曲がちりばめられて、
懐かしくも清らかな、しみじみとした心持にさせてくれた。
日本の叙情の真髄を伝えて下さる
栗本尊子さんは、本当に日本音楽の宝だと思った。

その中でも、鎌田忠良作詞、中田喜直作曲の「霧と話した」に感銘を受けた。
「霧と話した」
わたしの頬はぬれやすい
わたしの頬がさむいとき
あの日あなたがかいたのは
なんの文字だかしらないが
そこはいまでもいたむまま
そこはいまでもいたむまま
霧でぬれたちいさな頬
そこはすこしつめたいが
ふたりはいつも霧のなか
霧と一緒に恋をした
霧と一緒に恋をした
みえないあなたにだかれてた
だけどそれがかわいたとき
あなたはあなたなんかじゃない
わたしはやっぱり泣きました
一度、聴かれますように。
(伴奏の塚田佳男さんが素晴らしい。こんな心に添うピアノも聴いたことがなかった。
歌うように奏でる一音一音に思いが宿っていて、さぞ栗本さんも興に載られたに違いない。それもそう、塚田さんご自身が歌手でもあったというのだ)





![top[1].gif](http://www.mahoroba-jp.net/blog/top%5B1%5D.gif)