![winner_h13_13a[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/winner_h13_13a1.jpg)
佐伯 輝子
(寿町勤労者福祉協会診療所長、医学博士)
『致知』2006年2月号より
─────────────────────────────
「五年も前から先生を探してるんですが、
一向に決まらなくて困ってるんです」
自宅の医院と市内の診療所を掛け持ちし、
多忙な日々を送っていた私の元へ横浜市から
電話があったのは二十五年前。
五十歳を目前にした日のことでした。
現在、日本の三大ドヤ街の一つとして知られる
寿町(ことぶきちょう)も、当時は世間に知られておらず、
私自身もそこがどんな町であるか、見当もつきませんでした。
実際、それまでも何人かの先生に依頼したそうですが、
駅を降り、診療所に行き着くまでに誰もが引き返してしまう、
それほど異様な雰囲気の町だというのです。
夫は
「そんな危ない場所へ女が行くことはない」
と
断固として反対。それでも市と医師会からは
「何とか一年だけでもお願いします」
とたびたび電話がかかってきます。
そんな時、私たち夫婦の会話を
そばで聞いていた息子がこう言いました。
「ママを待ってくれている人がいる限り、
それを断っちゃいけないんじゃない?」
てっきり反対されるものと思っていた
息子の一言には驚きましたが、
あれだけ反対していた主人までが
「それじゃあやってみるか」と言い出したのです。
この時、女学校時代に担任の先生から聞いた
「いいかい、人間の意見は二人は複数じゃないの。
三人以上の意見があって
それがまとまった時にうまくいくのよ」
という言葉を何十年も経ってから実感しました。
初めての診察日、自動車で診療所前まで来ると、
木立ちで用を足している男性がいます。
仕方なく車の中で待っていると、
私の気配に気付いた彼が逆上し、
車におしっこを撒き散らしてきたのです。
木で車体を叩きつけられ、
怒鳴り散らしながら去っていった姿を見ながら、
これは大変な所へ来たと思いました。
診察に訪れる方は、泥だらけだったり、シラミがいたり、
下着も穿いていない、健康保険に入れない方など様々です。
しばらくすると、当初二十名程度の見込みだった患者数が
連日倍の数、多い時で九十名を超え、
待合室の廊下には人が溢れました。
「うるせぇ」「てめぇ、このヤロー」といった怒号が
わんわん飛び交い、落ち着いて診察もできません。
一度、待ち時間の長いことに腹を立てた男性が、
刃物を忍ばせて私に襲いかかってきたこともあり、
その後しばらくは恐怖心が拭えませんでした。
患者に首を絞められ、危うく死にそうになったこともあります。
入り口付近にいた男性が近づいてきて、
肩をつかまれたかと思うと「久々に女に触れた」という興奮からか、
私の首を絞めたまま痙攣状態になり、激しく震え出したのです。
専任のガードマンと職員が四人がかりで引き離してくれましたが、
腰が抜け、どっとその場にへたれ込んでしまいました。
私は寿町で死んでしまうかもしれない。
その思いはいまでもあります。
当時、診療所に訪れる人たちの中には、
逃亡中の身の上や、家を出て行方知らずになっている人も
珍しくありませんでした。
住人たちは寿町に身を潜めるように暮らしていましたが、
それでは悪の温床になってしまう、
なるべく明るみに出したほうがよいと思い、
講演活動などの際に、私はこの町の存在を
勇気を出して話してきました。
ただ、初めの頃は、皆のために
ここへ来たと思っていた私ですが、
いまになって、自分のためにここへ来たんだなと
思うことが少なくありません。
いまから十五年前、診療所での活動を評価され、
吉川英治文化賞の受賞が決まった前の晩のことです。
馴染みの患者から自宅に電話がかかってきました。
「先生、いつも賞を受ける時、私一人の力じゃありません。
スタッフ皆でいただいた賞です、って言うだろ。
分かんねぇのかよ。
俺たちもいままで“協力”してきたんだぜぇ」
確かに医者とスタッフだけいても仕事にならない。
患者さんも含めての受賞。
二十代からずっと医療に携わってきた私も
この言葉には目から鱗が落ちる思いでした。
診察をする上で、私は患者の方と目線を合わせる、
ということを常に心がけています。
だから「どこが悪いの」ではなしに、
「きょうはどうしたの」と尋ねる。
具合が悪いと聞けば、
「私は医者でたまたま治し方を知っている。
だから一緒に治してみる?」
と持ちかけます。そして時には、
一人の人間として声を荒げることもあります。
ある日、「ビール瓶で怪我をした」という男性が
診察室にやってきました。
巻かれてあったタオルを取ると、薬指はブラブラで、
皮一枚でついています。隣の小指はすでにありません。
すぐに手術をしようという私に、男性は
「指なんていらねぇから取ってくれ。
男の約束は、女には分かんねぇんだよ」
と言ってふてくされています。私はこう言いました。
「お母さんがあんたを産んだ時に、
この指がなくてもいいと思ったと思うの。
五体満足で生まれてくれて、あぁよかったと思うのが
女が赤ん坊を産んだ時の気持ちなんだよ。
それを尊重せずに自分だけの命だ、
指なんていらないなんて言ったら、
金輪際、女である私が許さないよ」
手術台のベッドで大泣きし始めた男性は、後日
「人に初めて怒ってもらえて、すごく嬉しかったんだ」
と教えてくれました。
休診の張り紙を出すと、いくら理由を言っても
「先生、やめるんじゃないだろうな」
「先生やめたら俺たち死んじゃうよ」と、
駄々っ子のようにごねる寿町の住人たち。
自分を待っている人がいる限り、
それを断ってはいけない――
二十五年前、息子から言われた言葉を噛み締めながら、
この生かされし命の使い道を考えるきょうこの頃です。
![20111006122458[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/201110061224581.jpg)
![winner_h13_13a[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/winner_h13_13a1.jpg)

![yasu1_img01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/yasu1_img011.jpg)
![s0115l[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/s0115l1.jpg)

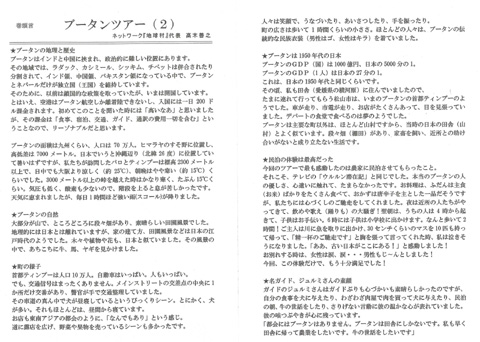
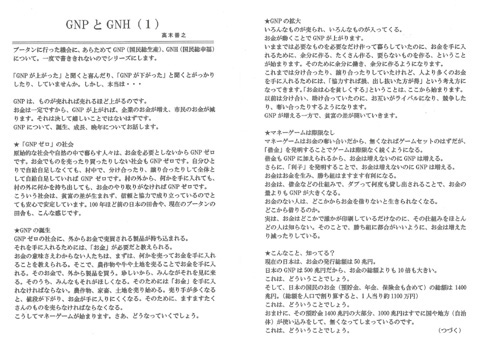
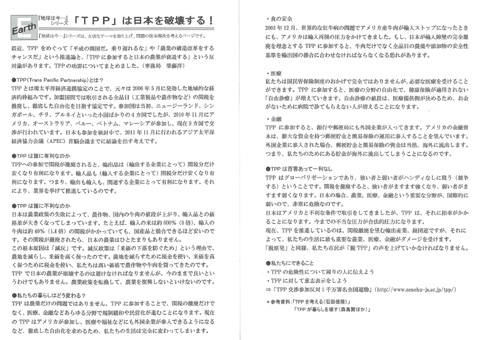

![CIMG0411[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG04111-150x150.jpg)
![cl_02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/cl_021-150x150.jpg)

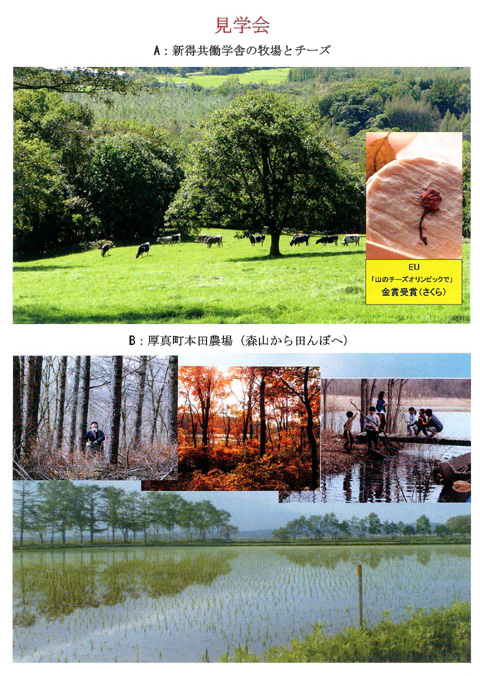
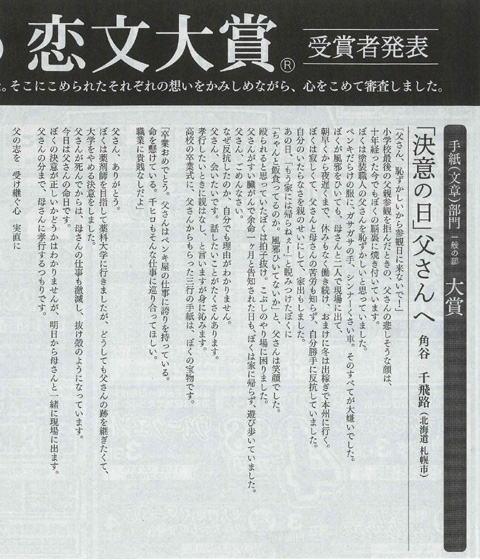
![6120[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/61201.jpg)
![f0121909_11444059[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/f0121909_114440591.jpg)
![12803156190001[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/1280315619000111.jpg)