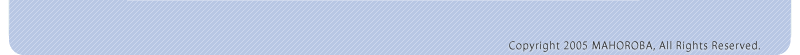|
「いや、古琴とか、七弦琴とか言っていた。」
「ほんとー、すごい!それは、どなたですか。」
「浦上玉堂」
「えーえー!!・・・・・」
もう、びっくりしたというか、それは唖然とするしかなかった。 もうかれこれ、二十年以上のお付き合いがあったのに・・・・・。
そんな事、今までおくびにも出さず、一言も洩らされなかった。 こんな近くに、あの浦上玉堂(呼び捨てて御免なさい)の子孫が居られて、長年お付き合いしていたとは、本当に驚いた。
最近、色々なご縁で驚くことが頗る多くなった。その中でも、このご縁は出色物で、別格だった。 それは、私の青年時の深い思い入れがあって、それと思い出が重なるからだった。
四十年も前、私が十八の歳に薬師寺の故橋本凝胤長老の大乗院におかせて戴いた時に、長老が私に、「岡さんと対談した記念に・・・・」と言って、数学者の岡潔先生のお書きになった『曙』(講談社、絶版)という新書を下さった。その中に、
「・・・・・私は胡蘭成さんから、孔子の作曲した七絃琴『幽蘭』のレコード(香港製)を貰ったが、全く感動してこんな音楽がありうるのかと思った。その後、さしもの西洋の古典音楽が、阿鼻叫喚と聞こえた。これが頭頂葉の音楽で、西洋の古典音楽は前頭葉の音楽、ドビュッシー以後のものに到っては側頭葉や体の音楽だと思った。
中国には琴は二つある。五(七)絃を琴といい、十三絃を筝という。日本にはこの後の筝の方だけが伝わったのである。・・・・・・」
この一文に、心が俄かにときめき、元々音楽志望の私は、この音楽を何とか聴きたい、出来ればやってみたい、と思うや、矢も盾もたまらず上京したのだった。七絃琴は、伏儀が八卦と共に創った世界最古の楽器である。その超古代の哲学と音曲に、聴かずして惹き込まれる媚薬のような匂いを嗅ぎ分けていた。
|